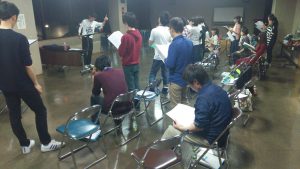ぐずついた天気の中、女性会館。
背中を意識することで体幹を意識。その姿まさに
マ ジ ン ガー Z!

ポジティヴにため息を吐くMEA。
何人たりとも自分の声の可能性を広げたい。
Pierre de La Rue「Laudate Dominum,Omnes gentes」
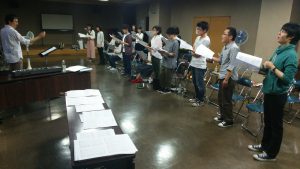
合わせにいくと小さくまとまる。つまらん。

向かい合う他パートの人の母音に重ねる行為。その隣人の向こうに透けて見えるMEAの母音を追求。それが曲を通してできるといいのですが、音やリズムがそこまでいけてなくて。
でも自分の嗅覚が言っている。このポリフォニーは良いと。
Mendelssohn 「Richte mich, Gott」

先生による発音口座。
英語になってしまっているのはどこのドイツだ?は さておき、この曲の持つ美しさと対極の自分の歌えなさに自暴自棄にならずに、取り組んでいきたいと思います。
最後に、信長貴富「こころよ うたえ」を歌いました。そして、
♪新入団、女声1名。2週連続!のこの二人のMEAへの希望がMEAの希望だと思います。しっかり応え合っていければと思います。
全体連絡の最後には、(先週の団内結婚発表に続き、今週は団内ではないけど)団員の結婚報告がありました。臨月団員も3名おり、おめでたいことが続きます。
結婚おめでとう、という時は常に、結婚おめでとうと言ってしまっていいのか、という問いかけや気遣いと隣り合わせです。
価値観の多様性、と簡単に言うもののね、もっと言うと、価値観の多様性の許容というか。
でも今日、その結婚報告をした団員への拍手の中、少なくとも、人と人の関わりの分、ポロリと感情の整理ダンスからしまいきれないものを感じました。