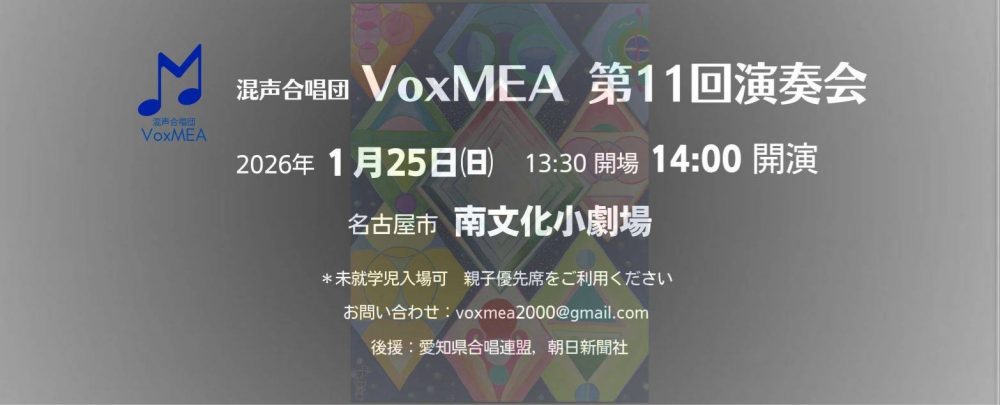今年の結果&演奏はこちら
2012年愛知県ヴォーカル・アンサンブルコンテストの結果
2012年アンサンブルコンテストの演奏と講評
アンサンブルコンテストから1ヶ月たち、いまさら感もありますが、来年の活動に繋げるためにメモしておきます。
2009・2010年の銀賞という結果から、演奏の質を向上するため、様々な課題に取り組みました。その結果、2011・2012年で金賞を頂くことが出来たと思っています。そこまでの取り組みと、現在の課題についてまとめました。
原点:2009・2010年の演奏
2009年アンサンブルコンテスト結果
2010年アンサンブルコンテスト結果
久しぶりに混声で出てみたものの、2年連続で銀賞という結果でした。
2010年の演奏です。
O quam gloriosum est (Tomas Luis de Victoria)
Super flumina Babylonis (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
このころに比べると、現在は和音の精度と曲のフレーズ感が向上していると考えています。
そのために取り組んできたことです。
取り組み① 発声の改善
2010年のちょうど今ごろから、発声がどうすれば改善できるかを投稿し始めました。
もともと、合唱経験の少ない方のための取り組みだったのですが、結果的に自分の発声の向上に繋がりました(笑)。
個人によって様々な課題があると思いますが、私にとっては『息をスムーズに出すための体の使い方』がとても重要だったと思っています。
その時のエントリーはこちら
ボイトレで気づいたこといろいろ
他にも必要なことがありますが、私の場合はこの体の使い方がボトルネックになっていました。このころから徐々に、ハモるために必要な、柔らかく響きのある発声について考えていたのかなと思っています。
取り組み② 和音の精度向上
2011・2012年と、1曲目は穏やかでホモフォニックな曲を提案しました。pやppを基調とする曲を歌うことで、常に支えを意識することができました。喉を固めない、柔らかい発声を土台とした演奏に近づけたと考えています。この辺りは下記サイトを参考にしました。
喉の基本フォーム | 吟詠の為のヴォイストレーニング
「ピアノ」を制するものは… | 烏は歌う
練習ではまず、和音の精度を高めることに集中しました。母音唱をかなりしつこく行い、音程・母音が変化しても各パートのピッチが揃うようになりました。その辺りは去年、アンサンブルコンテストの練習と課題で述べたとおりです。
取り組み③ フレーズ感の向上
練習ではスムーズな息の流れを意識しながら歌うため、練習ではブレスを取る位置と吸い方を意識しました。ブレスを取る位置はパート内できちんと揃え、そこまできっちり歌い切るようにしました。曲の雰囲気を崩さないように吸い方にも気をつけました。
課題
和音の精度を意識した曲作りを目指したものの、発声が固くなってしまう箇所がまだ残ってました。②と③の取り組みでのやり残しがまだまだあったのと、土台となる発声は常日頃の練習で意識して向上していきたいと考えています。
講評で指摘された『声を合わせようという意識が強すぎて声が前に出ていないところが多かった』は、まさにうちはその通りだと思っています。体が使えない状態で声を出そうとすると声が固まってしまうと考えて、選曲・曲作りを行い、ある程度の成果が出たと考えています。その良いところを損なわず進化していけるよう、来年も取り組んでいきたいなと考えています。