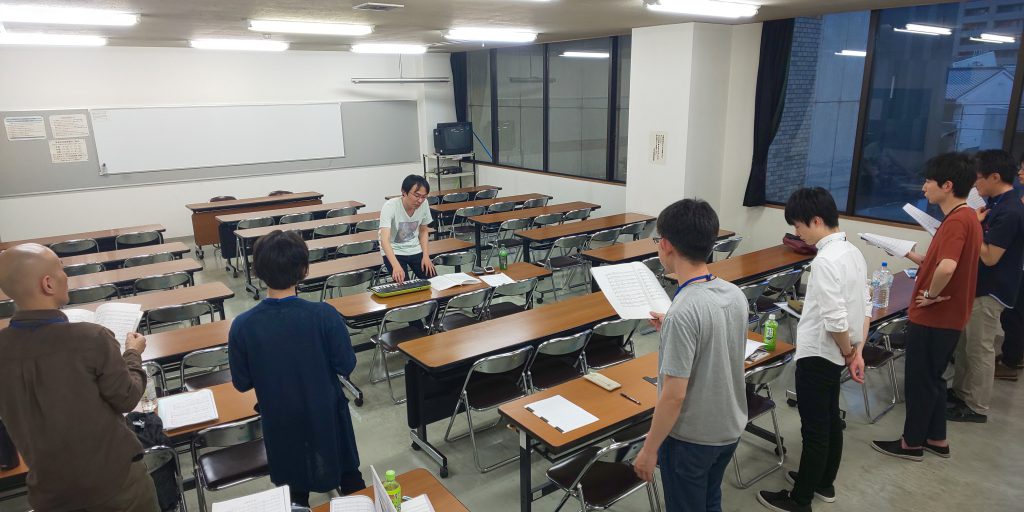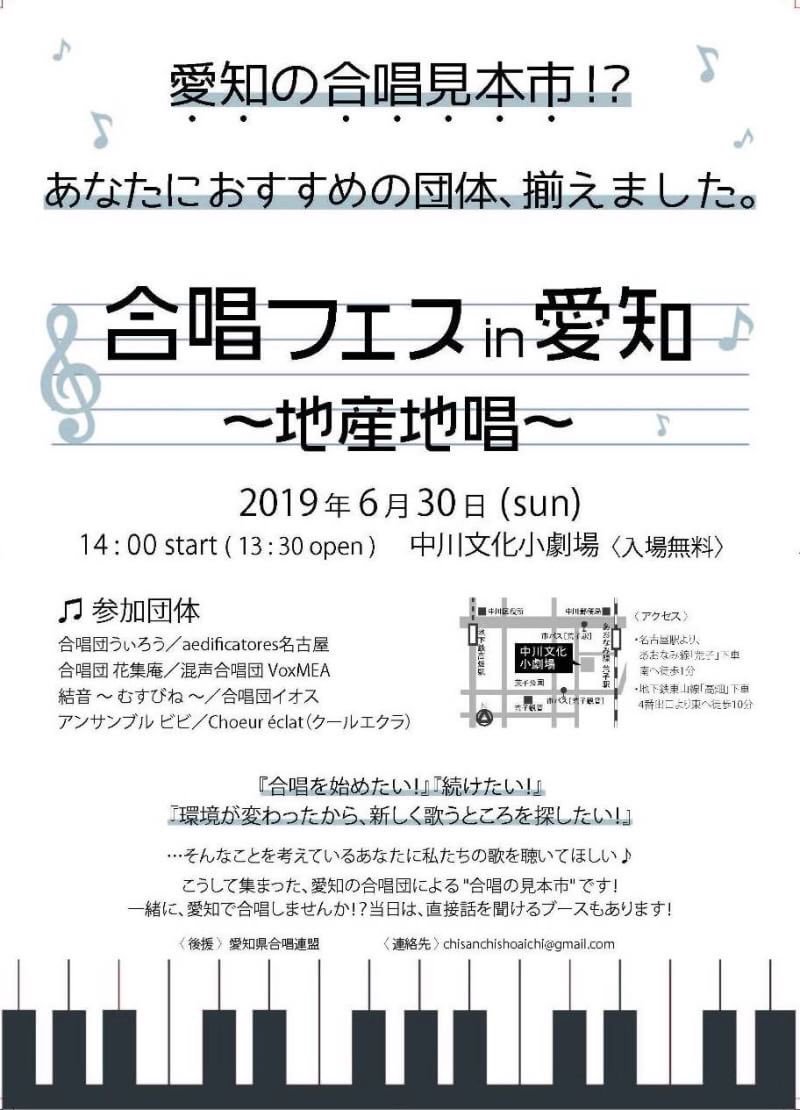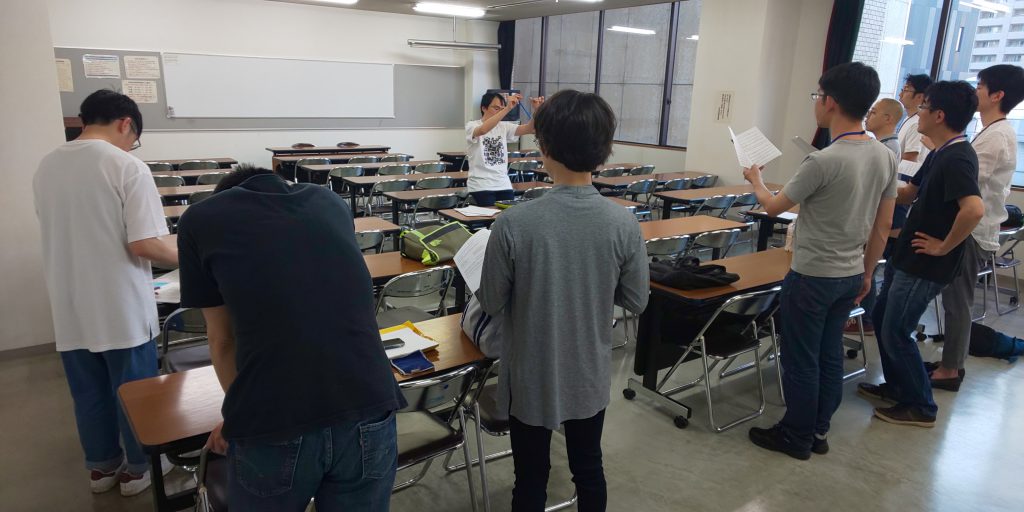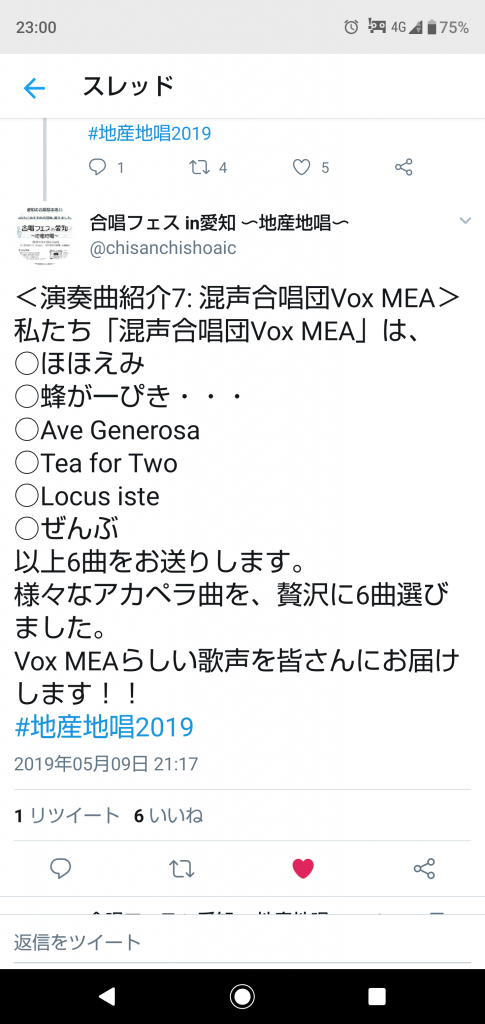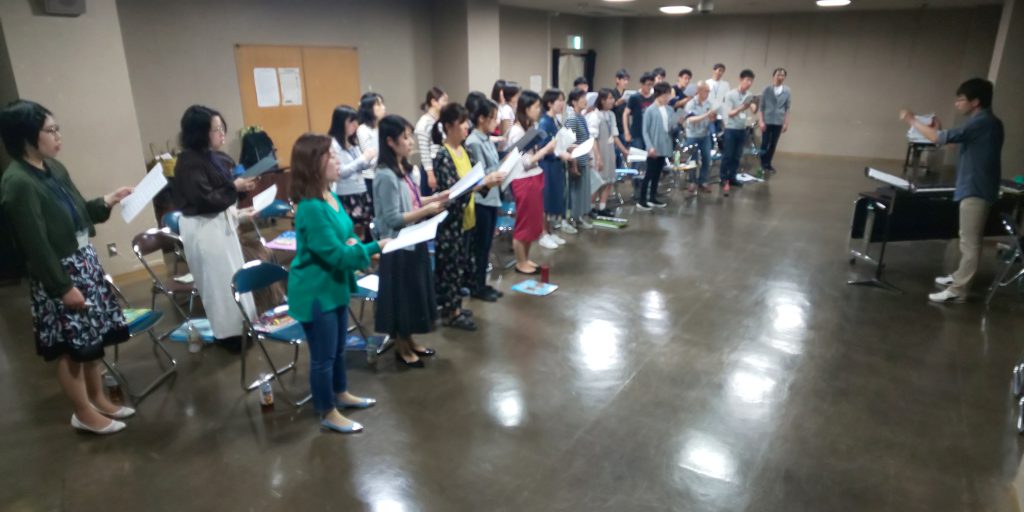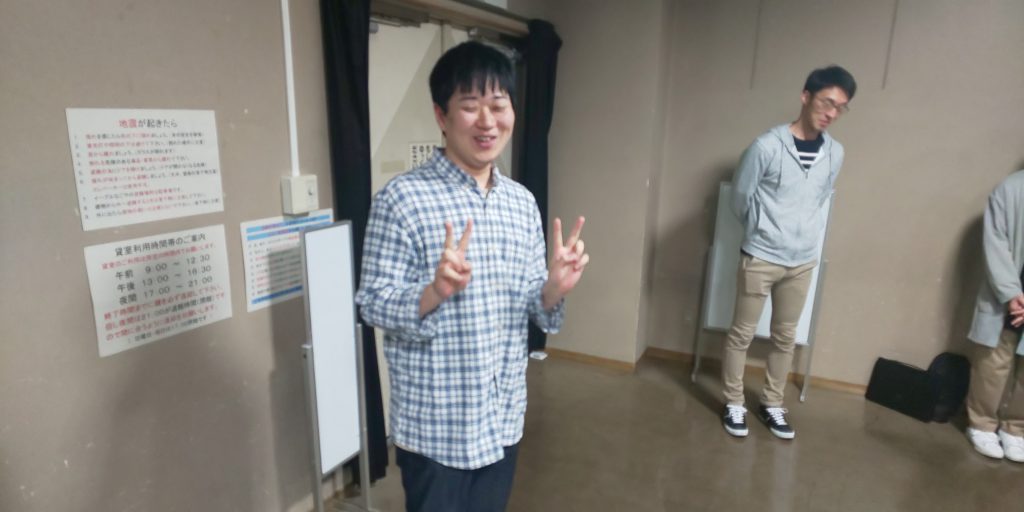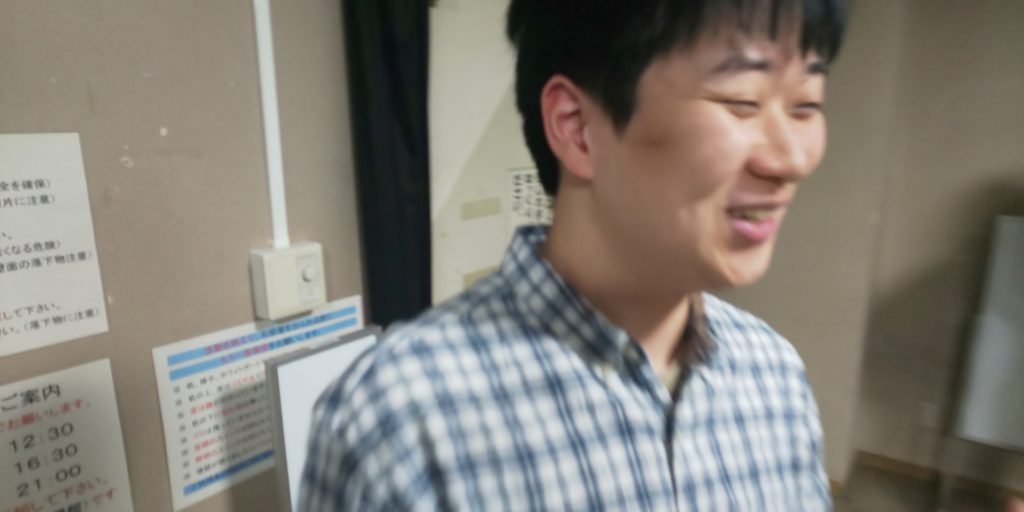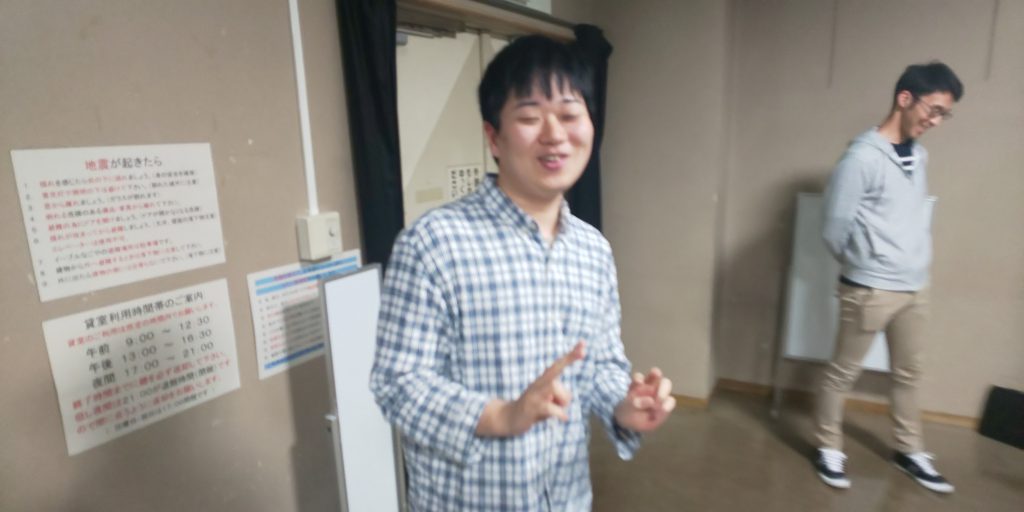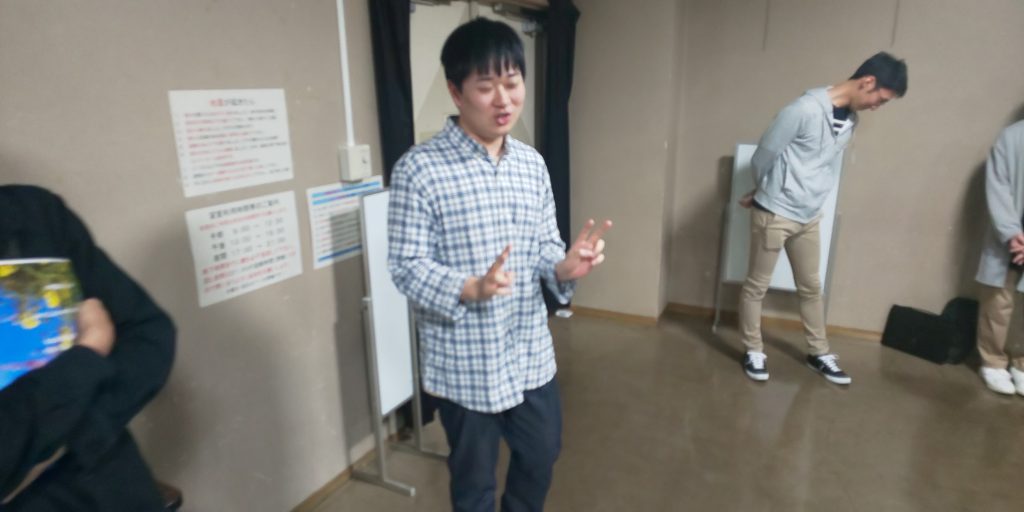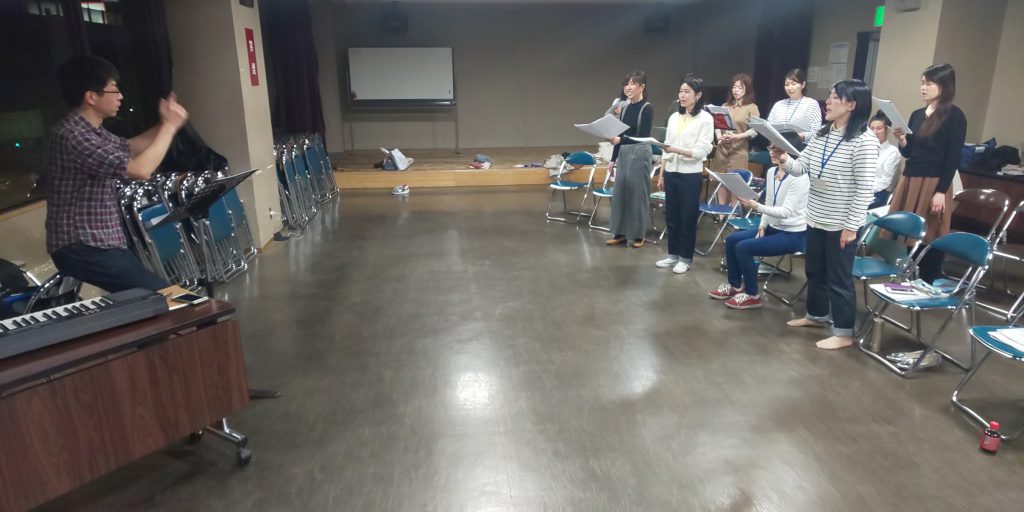文責:ひめ
こんにちは矢場公園、アートピア。
そして筆者的には初めまして、アンコン。

(やっぱり皆考えることは同じ??)
アンコンには、
一般部門(午前)に「Chor Benedict」、
ユース(午後)に「じせさっちょ」の2チームが出場。
我々じせさっちょは、午前中は中生涯学習センターにて最後の練習。
一般部門の演奏は見られませんでしたが、心の中でエールを送りました。

反省はありつつも、それぞれ良い演奏が出来たと思います。
響かないと聞いていたアートピアだけど、そんなことはなかった。

何人かは会場に残り、残りのユースの部の演奏を聴きました。
PRタイムでは、チームメンバーに『忖度』された現指揮者が一人で頑張ってくれました。
お疲れさまです。ありがとうございます。
でもいい加減「じせさっちょ」は覚えて欲しかった。

『じせさっちょ』は金賞を授賞。
◇Io mi son giovinetta (Claudio Monteverdi)
◇「自戒」から むじゅん (面川倫一)
『Chor Benedict』は銀賞+審査員賞(波多野均先生)
◇「Missa Pange Lingua」から Kyrie(Josquin des Prez)
◇我が抒情詩 (千原英喜)
私としては正直、嬉しいと思いつつも、「えっ金賞なの?」という印象。
もちろん、良い演奏が出来た結果でしょう。評価されたのは大変光栄です。
でも、まずは「ここが上手くいかなかった。失敗した」よりも、「最高の演奏が出来た!」と言えることが大事なのではないでしょうか。
また、私自身の反省ですが、自分(たち)の実力がどこまでのものなのか、まだよく分かってないことにも未熟さを感じました。
コンクール経験の薄い私が生意気なことを書いてしまいましたが、今はとにかく、アンコンお疲れさまでした。
次は合唱祭ですね。
頑張りましょう。



 5TH ANNIVERSARY CONCERT「paradox」
5TH ANNIVERSARY CONCERT「paradox」