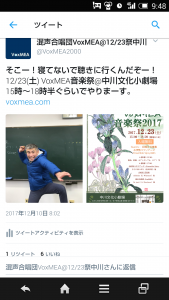冬期五輪開幕。いつの間に…と思ってしまう自分がちと情けない。快活に生きていかなくては。
そう、僕たちには歌があるではないか、と女性会館。
木下牧子「ティオの夜の旅」の2番『海神』

この組曲のめくるめく擬人化の世界に追われ汲々と(きゅうきゅうと ってずっと窮々と って思ってた!)するのではなく、夜間飛行に軽やかに並走していきたい。追い越し追い越されしながら。
この曲で2時間超経過。
一方、子連れ団員がかわりばんこに託児するMEAkids

出会いと別れを繰り返していく。それはいつの世もどこの国でもかわらないんだロッテ。
さて練習の最終盤は、団員同士で結婚するおふたり向けのソングを練習。鉄板の「糸」

僕が鉄板と言うと軽々しくとられるかも分かりませんが、ぐっと気持ちに入ってくる曲。街々まちまちの各家庭の各夫婦が窓の向こうで愛を育んでいる様子が目に浮かびます。
最後に、Beatriz Corona「Barcarola」
2014年度のコンクールで取り上げた曲です。
軽妙さを増して、海を渡り歩きたいです。
海…、「海神」と「Barcarola」での海の描かれ方の違うこと違うこと。捉え方と切り口は違ってよくて、ともに歌であるので、歌いこなしていきたいです。
団全体的には、周りに隣に声を出すことを依存していること を強く感じます。個の力を銘々が閉じてしまっている感じがします。隣に軸や核があれば、無類の強さを発揮する依存群。不自由さの自覚が殻を破るポイントだと思います。