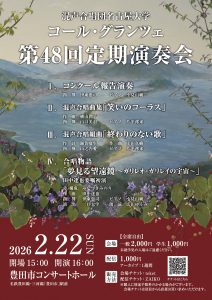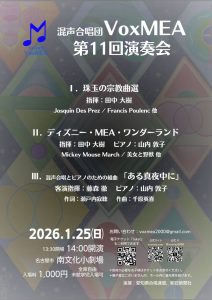取り扱う時代次第だが大河ドラマ好きな筆者はなぜかいまDVDで10年前にやってた「真田丸」を観ている。
合戦の模様があった。
市井(読み:しせい)の民衆を巻き込んだ合戦であった。
歴史に触れて知ったこと。
表面上のことだけ。
死ひとつとっても、学ぶ歴史上の人物の死、しか我々は知らない。
日本でいう中世、武士の世の3幕府だけ切り取っても、
数知れない戦い。
数知れない、死。
数知れないドラマ。
我々にも、ドラマ。
合唱団にもドラマ。
市井の、星の数ほどの合唱団。
同じ曜日、同じ時間帯、同じ市内でですら複数の合唱団がどこかで練習をしている。
合唱団の数だけドラマ。
1合唱団に何十の団員。
経てきたドラマ。
ドラマなう。
まだ見ぬドラマ。
感じながらイーブル名古屋。

大研修室。

高田三郎先生から。
愛の「あ」、A母音がどうこうじゃなくて、愛という言葉のあるべき「あ」が自分の口から明瞭に出てこない。なんかくぐもってる。
問題は歌唱力なのか、己の愛の深さなのか。
両方だと思うが、歌詞読みの練習はもはや、ミッション系の学校の宗教の授業のよう。
宗教曲に触れること。
宗教曲を通して、人間の根源に触れる貴重な営み。
今日まで合唱界で歌われているのがすべてだと思う。
複数の人間で歌ってこそのものがある。
マス(かたまり)で歌う。
民衆が群衆が同じ祈りを唱える。
その訴求力の高さといったら。
メロディーはもちろん、その辺りも宗教曲の良さなんだよなー。
名島啓太先生。
ずっと筆者が個人的に夢に見ていた名島先生の世界。
歌詞を入れて、だいぶそれっぽくなりました。はず。
土田豊貴先生。
名島先生のAmenとの違い。
難曲の攻略を通して、もっともっと入り込んでいきたい。
また来週。