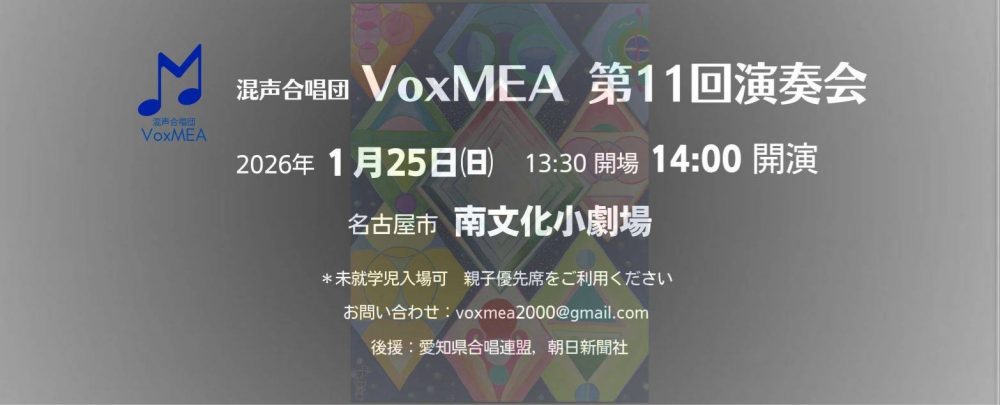1月から9・11レクイエムコンサートの音取り特別練習を行っています。
コンサートでご一緒するスコラ・カントールム・ナゴヤさんと練習を
相互公開しようということで、今回もスコラの方が練習に遊びに来て
くれました。
とっても伸びのあるきれいなソプラノで、大変勉強になりました
VoxMEAからもスコラさんの金曜日の練習にお邪魔させて頂いてます。
普段オーケストラ付きの大作はあまり取り上げないVoxMEAですが、
今回のジョイントコンサートでの交流を通じて、お互いのいいところを
吸収して成長の糧にしていきたいと考えています。
ご期待下さい!
「練習」カテゴリーアーカイブ
10月30日の練習
明治村トリエンナーレに向けた練習を行いました。
練習内容はルネサンス曲とバッハ”イエスよ我が喜び”で、バッハが主体でした。

ルネサンス曲は結婚式で歌った”Ave verum corpus”、”Ave Maria” を練習しました。柔らかい響きで歌えて、なかなか良い演奏ができたと思います。反面、コンクール課題曲の “Ne timeas, Maria” は久しぶりに歌ったせいか、あまり良いところのない演奏で、指揮者からは『(コンクールで良かったのが)腐ってるね』と言われてしまう始末…(泣)。次の練習では挽回せねば。
バッハの”イエスよ我が喜び” は3月の公開録音以来、半年振りの演奏になります。コンクール後で練習回数も少なく、公開録音後に入った団員もいますが、パート内でのフォローのおかげで良い感じに形になっています。
この日のバッハで、指揮者からは『息の流し方』、『体の使い方』を多く指摘されました。メリスマの箇所で息を流せず、結果、音程が上ずる・走る・音が浅くなるなどし、音の跳躍のところでは不要に音が大きくなったり、音が固くなったりしました。
難しい曲ですが、こういった課題に取り組むことで個人の実力は確実に向上していると感じています。
練習後は飲み会が企画されていました。

何か特別なことがあったわけでもない、普通の飲み会でしたが結構な参加者が集まりました。新しく入られた方ともお話することが出来ました。普段の練習ではなかなか話せない人とも、こういう場で色々な話を通じてお互いの考え方を理解し合えるのは本当に面白いです。

充実した練習を重ねて、再来週の明治村トリエンナーレでは最高の演奏をしたいと思います。
10月9日の練習
明治村トリエンナーレと、明日(10月10日)行われる団員の結婚式で歌う曲の練習を行ないました。

Ave Maria (J.Arcadelt)
Ave verum corpus (W.Byrd)
翼を下さい (編曲:渡邉なつ実)
ラシーヌ賛歌 (G.FaurクJ羽
夢みたものは… (木下牧子)
新旧の団員が明日の結婚式へお祝いに集まるということで、今日の練習は半端ない人数が集まりました。外はすっかり涼しいですが、練習場は暑いくらい(笑)。本番前ということもあって、気合の入って集中した良い練習でした。
中村先生練習
中村先生に練習をみてもらいました。
曲は明治村トリエンナーレと団員の結婚式で演奏する“Ave Maria (J.Arcadelt)”、“Ave verum corpus (W.Byrd)”、“ラシーヌ賛歌 (G.FaurクJ羽”でした。中村先生曰く『残念ながら結婚式に行けないので、ここで本番レベルに仕上げてお祝いします(笑)』とのこと。

“Ave verum corpus”はまずまずの練習ができました。指摘された『子音から音をイメージして出す』ことは、苦手な音の立ち上がりを克服するために意識していきたいです。練習を通じて曲のイメージを表現し、感じることができたのかなと思っています。
“Ave Maria”は残念ながら中村先生の期待に応えられない出来でした。音が完全に取れていない、弱声で入るフレーズが多い、色々な理由があると思いますが、とにかく声の立ち上がりが悪かったと感じました。他にも目前の音を意識しすぎてフレーズ感が無くなる/息が最後まで持たない等々、ちょっと前までコンクール課題曲をやっていた経験が活かせない『リセット』された出来でとても残念です。

中村先生もご立腹(嘘です)。
“ラシーヌ賛歌 (G.FaurクJ羽”は時間が無いこともあって、発音を中心に指導してもらいました。フランス語の発音はシツコク繰り返し覚えないといけないなと実感しています。
練習後は中村先生とご飯を食べに行きました。去年の同じ頃行ったお店を再訪です。

中村先生もお酒が入ってノリノリ。こういうときに名ゼリフが出ます(笑)。

練習は今一歩のところもありましたが、そういった反省や他愛も無い話、いろいろな話をみんなでワイワイと意見交換することが出来た、とても良い場でした。
明治村トリエンナーレに向けて
明治村トリエンナーレで演奏する曲が決まりました。
・教会音楽の原点①
Ave Maria (J.Arcadelt)
Ave verum corpus (W.Byrd)
Ne timeas, Maria (T.L.Victoria)
・教会音楽の原点②
Jesu, meine Freude, BWV227 (J.S.Bach)
・日本の歌謡曲
翼を下さい (編曲:渡邉なつ実)
乾杯(編曲:信長貴富)
・教会音楽の原点③
ラシーヌ賛歌 (G.FaurクJ羽
“教会音楽の原点①~③”は暫定で名付けたステージ名で、われながら実に味気ない。そのうち更新します(笑)。

前回(2007年)に撮った写真で、微妙に違う写真をトップに使っています。
今回演奏する曲目はここ一年で歌ってきた曲をほとんど全部盛りですね。練習する時間も少なく非常にしんどいのですが、少ない時間で集中して曲を仕上げる訓練になると思います。
こういったときは、これまでの練習で言われてきたことを最初の練習で当たり前のようにできることが重要になります。曲が新しくなったら歌い方もリセット!なようでは何年たっても上手くならないんですよね…。
次回の中村先生練習では“Ave Maria”と“Ave verum corpus”を、コンクールで学んだことを活かして、きちんと歌いたいと思っています。全体的には前回の練習で言われた『スムーズな息の流れ』と『母音でのピッチ変化をなくす』、『最後まで歌い切る』ことをもう一段高いレベルで実現していきたいですね。
9/4 練習と今後の活動予定
久しぶりの更新です.コンクールで燃え尽きた…わけでなく,公私ともども忙しく更新を怠っていました(´・ω・`)ごめんなさい.コンクール後,VoxMEA は次のイベントに向けた練習を行っています.近々の日程は以下のとおりです.
9月5日(日) : 結婚披露宴で演奏
夢みたものは… (木下牧子)
乾杯 (編曲:信長貴富)
10月10日(日) : 結婚披露宴で演奏
ラシーヌ賛歌 (G.FaurクJ羽
Ave verum corpus (W.Byrd)
Ave Maria (Arcadelt)
翼を下さい (編曲:渡邉なつ実)
11月14日(日) : 明治村トリエンナーレ2010「第3回芸能・芸術祭」で演奏
これに併せて,9月18日(土)には中村先生による『Ave verum corpus』『Ave Maria』の全体練習があります.
VoxMEA は団員・元団員の希望により有志で結婚披露宴で歌うことが多いです.歌う曲は基本的に新郎/新婦の意向を反映していますが,ここで歌った曲を明治村トリエンナーレでも演奏しようという魂胆もあります.あざとい!(笑)

この日は明日に控えた『夢みたものは…』『乾杯』と,来月演奏する『ラシーヌ賛歌』の練習をしました.写真では分かりにくいですが,奥の女声の密度が高く,人数比ではほとんど女声合唱団でした(笑).
なかなか練習する時間も限られていますが,できるかぎり一番の演奏をして仲間の門出をお祝いしたいです.
夏合宿を行いました
コンクール前の合宿を行いました。

初日はまず、課題曲のパート練習~個人アンサンブルの練習をしました。
個人アンサンブルでは相変わらず緊張しましたが、前回の反省を活かしてアガり対策を実践してみたら、結構うまく歌えたと思います。
超てきめん 緊張 解消法 | 知識の宝庫!目がテン!ライブラリー
アガりを克服する個人的なポイントは“アガっている状態を意識的にコントロールする”、“常に腹式呼吸を意識する”でした。
アガりって心理的なものだと思いがちですが、wikipediaでは「心拍数120を超えるとパニック状態と判断される場合がある」と、身体状態を表す心拍数とパニックが結びついた説明がされています。
私は人前で歌うときに心臓がバクバクいっているのが分かるくらい良くアガります(涙)。今回の個人アンサンブルではアガってること自体は仕方ないとして、自分の心拍数を意識し、パニックにならないように気をつけました。
腹式呼吸って、歌うための基本なんですが、緊張すると腹筋が硬直してうまく息を吸えないんです。目がテン!ライブラリーで書いてありますが、練習の最初でやる“脱力した良い姿勢で腹式呼吸をする”だけで結構リラックスできました。
また、通しで歌っているなかでも、休みの際に脱力して息を吸うだけで結構楽に歌えるようになります。

初日の夜から2日目は課題曲と自由曲のアンサンブルをしました。
さすがに本番一週間前だけあり、緊張感のある充実した練習でした。
この合宿を通じて、一人ひとりから、『うまく歌いたい』という気持ちを凄く感じました。実際に、この合宿で歌い方が一段とうまくなった人も結構います。本番はみんな、これまで学んだことが活かせる最高の演奏をしたいです。

課題曲あれこれ
コンクールまでもうすぐですね。暑い日が続くので体調には気をつけたいところです。

『聖☆おにいさん』のヒトコマ、受胎告知のパロディです。
この漫画、巻が進むにつれてネタがどんどんマニアックになってる(笑)。
歌を歌うにあたって、言葉の意味や物語、時代的背景を理解することも、うまく歌うのに繋がります。
■言葉の意味、発音
私の経験ですが、言葉の意味を分からずに歌っている人は結構損しています。
例えば練習でやった、「utero」のウ母音での掛け合いは昔の人が持っていた、「胎内」の神秘的なイメージを出すこと。この意味を意識して歌うことができるようになると、更にうまくなります。
慣れないうちは楽譜に言葉の意味を書いて、旋律と言葉の意味を結ぶクセをつけたほうが良いです。ってそろそろ暗譜している人も多いと思いますが(笑)。
発音も、慣れないうちは楽譜に書き込むことをお勧めします。ラテン語の読み方が分からない人は以下のサイトを参考にすると良いと思います。
合唱団ぽっきりの演奏情報など
途中から練習に加わった人は意外と勘違いしていることが多いので、不安なら恥ずかしがらずに周りに確認すると良いです(聞くは一時の…ってやつです)。
■物語、時代的背景
物語については2010 G1:Ne timeas, Maria の背景 (1)に書いてあります。受胎告知って感動的なんですが、悲劇的な側面も持っているということを知ることが重要です。この物語と Victoria の作った音楽と合わせて、どういう表現するかということが合唱の醍醐味です。
時代的な背景を知るのには2010 G1:Ne timeas, Maria の背景 (2)でお勧めしたサイトを見てみるのをお勧めします。同じ芸術っていう枠の中で、音楽と美術が進化しているんだな、っていうことが一目で理解できます。
Ne timeas, Maria の時代的背景には音楽史における”Ne timeas, Maria”の位置づけと、表現の一部が書いてあります。
コンクールまでもう少し。基本を忘れずに歌っていきましょう。
中村先生練習とビアガーデン
中村先生にコンクール課題曲・自由曲の歌い方を教えてもらいました。

■“いつも”腹筋から頭までスムーズに息が流れることを意識する
最初から最後まで言われっぱなしでしたね。基本なんですが、全然出来ていないことが良く分かりました。
勉強になったのは『砂時計』で、ソプラノが“あのときは”で高音に跳躍しながらfからppになるところです。喉を締めて高音を出そうとすると、ここの表現が出来ないので、響きで音量を調整していることが、見ていても良く分かりました。
他には『どんぐりのコマ』のベースのパートソロ“どんぐり”の入りで”Do”を出すところ、低音ということもあるのですが、破裂音を出そうとすると無意識に胸から息を出そうとしていることが実感できました。そうやって出される低音は胸で響いているような、響きが濁った音になっているんですね。
■母音が変化する際のピッチを統一させる
『砂時計』で最初のアルトのパートソロ“ときはおちる”のところ、音の跳躍があるのですが、それを無視して一定の音で歌うことで、母音が変化する際のピッチを揃えていました。母音のピッチは個人で結構クセがあると思います。私を例に出すと“イ”母音は上ずり傾向で“ア”母音は下がり傾向です。この辺りを今後どうにかしていきたいと考えています(涙)。
これと母音の出し方についてで書いた、あいまいな母音の出し方が出来るようになると、『どんぐりのコマ』で女声が“もういいかい”、男声が“ゆきたいな”で延ばすところ、母音が違うのに凄くハモってたのは、歌っていて良く分かったはずです。
この日の練習でやったように『ウ→オ→ア→エ→イ』の順で同じ音を出す練習をやることで、母音間のピッチを揃える口の開け方、響かせ方を覚えることが出来ます。前の日にハミングで課題曲練習をやりましたが、これも同様に、母音を入れないことで音程の意識が正しいかチェックしています。
音程に関する指摘を受けたときに、母音をチェックして自分の母音の出し方のクセを見抜くことは、上達するために重要だということがよく分かりました。
■最後まで歌い切る
息が続かないこともあるのですが、言葉の最後はどうしても抜けてしまいがちです。ただ、日本語としての意味を考えると最後まできちんと伝えることが必要となるシーンがあります。“いる”なのか“いない”なのか、“泳ぐ”のか“泳がない”なのか、きちんと伝えきることを指導されました。言葉として相手に伝える際に必要なことを、きちんと理解して歌うってことの重要性を教わりました。
他にもいろいろと教わりました。練習に来られなかった人は、来た人にいろいろと聞いてみた方が良いです。
練習後は中村先生と有志で中日ビル屋上のビアガーデンに行きました。

自称晴れ男(?)中村先生のおかげもあって、カンカン照りでした。暑い。
水分補給にビールを飲むしかない(笑)。


日が暮れるとビル風が良い感じに吹いて、美味しくビールをいただけました。
どんぐりのコマ(五つの童画)の詩の解釈
つまんでとがらせた
『どんぐりのコマ』も含め、この曲集に含まれている曲の言葉は割と平易で、一見すると子供が書いた絵の情景を表現した詩に見えるんですが、理解しようとするとその深いメッセージ性に気付くことができます。
まるで子供に絵本を読み聞かせる時に、こっちがその絵本が発信しているメッセージに気付き、教えてあげているつもりが逆に教えられているような、そんな体験です。
この詩集を五つの“童画”と名付けたセンスは物凄いことだと思います。
…というわけで、相変わらず勝手に解釈をしていこうと思います。
さっそく詩を読んでいきます。最初の「なぜとがってる」と問いかけをしている人はだれでしょうか。おそらく子供なんでしょうね。Sop.が担当なので男の子、女の子に関わらず小さい子だと思います。
そこから先の“樫の木に”以降は詩にインデントがついているように、情景の説明です。ここでの
いっぱいなりました … いっぱい(実が)生った
まあるくなりました … 丸くなった、丸く(実が)生った
その後の“樫の木になりたい” … 文字通り
というように、同じ“なる”という文字でも言葉ごとに意味が推移していきます。
この後は擬人化されたどんぐりの物語です。擬人化するには物語の書き手がいるので、書き手兼読み手は最初に出てきた子供なんでしょう。いろいろな大きさのどんぐりを見て、いろいろと想像を駆け巡らせたと思います。「大きいのは大きい樫の木になりたいんだな」とか…、あれ、じゃあ小さいどんぐりは?普通、樫の木って大きいです。この考えだと小さなどんぐりは何にもなれませんよね。
ここで子供は、頭の中で神さまを作ります。優しい神さまが、小さなどんぐりに対して『コマになっていいんだよ』と、頭をつまんでとがらせたのだと思いつきました。だから大きなどんぐりも小さなどんぐりも喜んで飛び降りて行く情景が子供の頭の中で生き生きとイメージされます。
“どんぐりみんな”以降は、子どもが言葉としての『どんぐり』から、種としての意味を持つ『樫の実』を理解するんだけど、そうやって考えるとみんな幸せになれないので、神さまがわざと樫の実を『とんがり頭』にして、『コマの足』とするストーリーが作られる過程をまとめています。
“どんぐり!”は感極まった子供の叫びでしょう。“からからくるり”でどんぐりのコマがカラカラと音を立てて回る様、カラカラと乾燥した情景を思い浮かばせ、続いて“落ち葉もまわる”“風もまわるよ”と、からっ風が吹いて落ち葉が回る様子を子供の視点から、すべての見るものが新鮮な視点で描かれます。
“こどもたち”以降、フィナーレはどんぐり・子供たちを最も俯瞰的な目で見た立場から描かれます。この光景を見ているのは、この詩を書かれた高田敏子さんであり、この詩を読んだ私たちです。
…というのが私の解釈です。情け無いことに全く自信がありません(涙)、変なところがあれば優しく突っ込んでいただけると助かります。
五つの童画について説明がされていましたので、今回はそれを念頭に詩の解釈を行いました。
調布市民合唱団ホームページ
1968年の作品。 ビクターからリリースされている『三善晃作品集1』の中で三善晃は、高田敏子さんに、「人間と地球全体をくるむ愛を歌う、というテーマで、詩心をもっと ひろやかに、少しばかりのフィクシャスな寓意をはさみこんだ詩を書いてくださるようお願いした。」と書いている。
私の詩の解釈は途中から大分暴走しています(笑)、愛を与えてくれる神様って人間が作り出したものなんじゃないかなと思い、こういう解釈になりました。出来る限りの言葉を使ったつもりですが、力足らずで伝わりきれていなければごめんなさい。
最後に、子供がらみで感動した動画を紹介します。