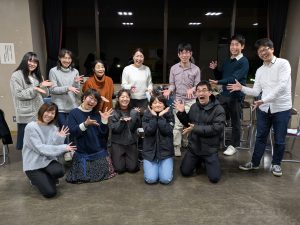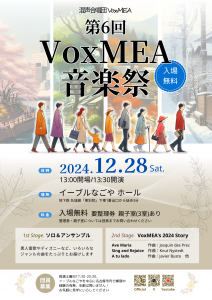イーブル名古屋。
ブレスしてメタモルフォーゼ。
♪「ある真夜中に」千原英喜
曲終盤に着手。
くちびる:物質的欲求
よろこび:精神的欲求
この対比が描かれている。
合唱を通して、詩に触れる貴重な機会を得ている実は。
かと言って、ここで現代が失ったもの…うんちゃらかんちゃらと論じるまで、まだ自分が曲の境地に達していない。
ただひとつ言えることは、数多く転調していく中で、
(言い換えると、人生が翻弄されていく中で、)
決してブレない己の確立をこの音楽は求めている。
♪「寂庵の祈り」千原英喜
筆者は先週の高校アンコンのお手伝いに行って、この曲の演奏を聴く機会がありました。
千原サウンド+寂聴の世界観。
こりゃ難曲だなとの認識でもって臨んだMEA練でしたが実際、歌って幸せになれるー、とかそんなきれいごとではないなって、人生を語るってことは。語れた気にさせるのがこの曲の魔力。
ここで先に、
♫新入団、男声1名。
12月から見学に来てくれて、音楽祭でも真摯に耳を傾けてくださっていました。これからよろしくねん。
あと、見学者も1名。
帰り道、指揮者と3人で金山まで歩きました。
入団ではなく今後、キミの力を借りる局面が訪れるかもしれない。ひょっとしてそうなったらよろしくねー。
最後の30分で、
♪「美女と野獣」ディズニー

年末の音楽祭でスパカリ組だった筆者は苦戦を強いられる。
しかも次回演奏会までの練習計画では、次にこの曲を取り上げるのは8月だって。マジでー?
(この文脈、考え抜かれた文章構成)
そうそう、その次回演奏会が決まりました!
我々、混声合唱団VoxMEAは、
2026年1月25日㈰午後に、
名古屋市の南文化小劇場にて、
第11回演奏会
を行います。
その演奏会に向けての団テーマを設けました。せっかくなんでご披露させていただきます。
「声を一段階、成長させる」
です。
勘違いしてほしくないのは、これはあくまで手段であり、
成長させ、て、
じゃあどうすんだと。
どうなりたいのかと。
個々の、団の、目標めがけて取り組んでいきたい。
練習の景色が変わった。
そういうワタクシ?
声を一段階成長させて、
音楽をより高いレベルで表現したい。
この一点。
揺るぎない。
揺るがない。
最後に情宣。

混声合唱団名古屋大学コール・グランツェさん
第47回定期演奏会
ここでまた示唆を筆者は得た。
グランツェさん、最終ステージが委嘱初演。1カ月後であるにもかかわらず、その楽譜がまだ来てないとか。
それをどうこう言うわけではなく、もちろん学生さんで、それ以前に全国レベルの大学合唱団。練習頻度や体制,圧力,エネルギー…精力的に委嘱初演をこなしていく。合唱界のトレンドだと感じる。
比較しては失礼だが、我々は地道にしかできない。一曲一曲、練り上げていきたい。
たといそれが、トレンドと逆方向であっても、全速力で一歩一歩を踏みしめたい。
そこに我々の音楽があるとの確固たる信念がある。
次週はと、おっと、新栄ね、東生涯学習センター。