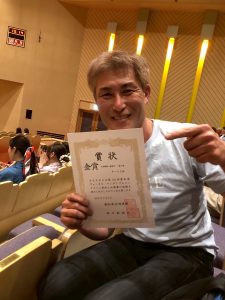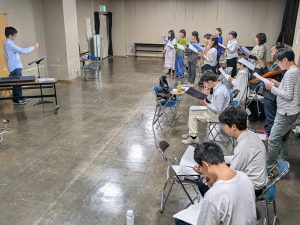東別院のイーブル名古屋。
発声でスタートできると、やはりその夜は調子が良い。
上西メソッドのひとつを思い出してみる。
「浮力と写し鏡で水面を押す力を感じ、下半身で歌う」
水面を滑っていく、筆者はジェットスキーをイメージ。
浮力とは、。
ブログをしたためつつ調べる。
液体に浸かる物体には、物体が押し出した液体の重量に等しい浮力が働く、というアルキメデス法則をネットで見つける。理論的にも合ってる。
そもそもイメージの部分が大きいし、実際に曲を歌っているときに実践できているかどうか、というモヤモヤが常に付きまとう。
でもいろいろ考えながら、少しでも歌が上手くなりたい。
 で、曲に入る。
で、曲に入る。
上を向いて歩こう
見上げてごらん夜の星を
おぼろ月夜
りんごの唄
四季の歌
ふるさと
どう声を出していけばよいか、引き続き、いろいろ考えながら歌っ、てしまう。
しかし、そういう意識が、聴こえていく音楽にどこまで反映されるんだろう。ここでまた考えてしまう。とにかく、
これらを歌う機会についてはまた報告できると思います。
続いて、コンクール曲に取りかかる。

「声を一段階、成長させる」
これは当団の今年の共通目標である。
5/6(火祝)にアンコンがあった。

一般の部で金賞。狙いに行った賞を獲った。
よかったよかった。
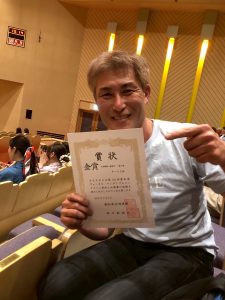
じゃあ次なる問い。
声が一段階成長したから金賞が獲れたのか?
その手応えがないんですよね。ないから考えたい。考えて答えに、そして言葉にしなければならない。
当初(今年年明け)の
自分のイメージでは、団員とは違う次元で頭ひとつ抜けた歌声を獲得し、みんなを引っ張っていく。そんなある意味、気概みたいなものはあった。
その気概の、分量だけは良し。損ないたくない。
でも今(GW明けたぐらい)、
まず思うのは、声で引っ張っていく、ってのはおそらく間違いであり幻想で、そうなったとして混声合唱団という構造上、パートの声を殺してしまうこととほぼ同義、だと言ってよいであろう。
三輪先生のボイトレでの、チームの「ここがおすすめポイント」を見つけておくとよい。という言葉を反芻する。恥ずかしながら、現時点で言葉にすれば、
「意識してアンサンブルをしようとしている点」
って筆者は言ってしまいそう。
上手ければ無意識にできてしまうところを、上手くないので意識してやってます、ってスタイル。
声をアンサンブル仕様にすること。
それも成長のひとつだと思う。
「明るい声を出すこと」
今日現在での、声の一段階の成長、と位置付けたいと思っている。
何故、明るい声が必要か?となにかのインタビューで問われた際の答えを持っているべきで、筆者は、
「曲の表現を、より正しく行うために必要だから」
という答えを持って、そして動いている。
先週は、
次の高い音に行く、首の後ろから頭頂までの準備動線を金輪際、「翼を広げる」と呼ぶこととした。
それが1週間前は一番大事だと思った。それはそれでよいし、実際そう思って今週も歌ってた。そのことを蓄積と言っちゃってよくって、
今週は、
明るい声を出せることは成長のひとつとみなしてよい。
という境地にたどり着いた。
それもまた良し。ということです。
最後にMickey Mouse Marchを、団員伴奏付きで。
この曲は時間がかかる。時間がかかる分だけ、「耳スキル」を高めなければならないし、「苦労対効果」という果実も得なければならない。うーむ、勢いで言葉にしたはいいが、あまりにも重たくなってしまった。。
簡単に言うと、1回、あー歌ったー、って感覚持ちたいです。
次週は新栄、東生涯学習センターです。





 で、曲に入る。
で、曲に入る。