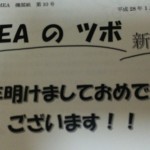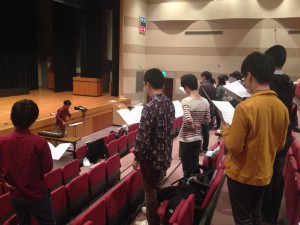次回演奏会、決定いたしました。
今年12/25(日) 中川文化小劇場 です。
ある団員の言葉で、いま自分のいる集団、それはコミュニティであれ、偶然居合わせた電車の中であれ、それを
「自分 対 周り」とみるか「自分も含めた集合体」とみるか
という示唆です。
この気の持ちようはたいへん大きく、とかく独りよがりになりがちなところを「自分も含めた集合体」ととらえることであらゆることの自分の見方を換えられることができます。
批判の前に自分も携わっているではないか、と。その前後に自分の行動言動でなにかできることはなかったか、と。
そういう立ち位置でいられて初めて、自分が誠にその集団をどうしたいと思っているかという段階に行くことができます。
使いやすい言葉で、物事の周囲をつかず離れずで凌いでいくことは簡単で、ともすれば多くのことに自分を費やしていることが見えてきます。
「合唱が好き」「VoxMEA(読み:ヴォークス・メーア)が好き」と言います。パッとそう言えることも大事ですが、もう少し濃度を増したいなと思います。まだまだ足りませんね。
♪新入団、女声1名