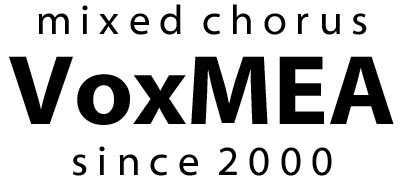ブレスのこと
今年は課題曲がルネサンス曲ということもあり、練習のなかで個人アンサンブルをする機会も多いと思います。これって別に度胸試しとかいうわけではなく(そういう観点もありますが)、「ひとりひとりが優れた歌い手であり、そういう人達が集まった合唱を演奏したい」という創団当初からの信念の顕れだったりします。ひとりひとりの歌を聴いていると「この人、ここの音程がいい」とか「表現力あるな~」とか、日ごろ一緒に歌っていると分からない、意外なことが分かったりしますよね。そんな個人アンサンブルでは避けては通れないブレスの問題について調べてみました。
■ 声を出す仕組み
基本的な事として、声を出す仕組みについて確認します。声は呼気が声帯を通過することで生じます。声帯は伸縮させることによって音程の高低を制御することができます。この内容の詳細については以下のサイトが詳しいです。
声帯と声の関係 | 吟詠の為のボイストレーニング
なので、ブレスの勢いが足りていないと、そもそも十分な声量を出せません。声量が足りていないと、正しい音程でも個人アンサンブルではハモったように聞こえません。また、パート同士の音が聞こえないとピッチが狂っていくことが多いと思います。
でも肺活量の低い人って、声量を出そうとするとすぐに息が持たなくなりますよね。
■ ブレスを増やす
調べるまで、この辺りを勘違いしていました。「肺活量って個人差があるからな~」と思っていました。
9なぜ腹式呼吸が必要? | 声の豆講座
よく私は肺活量が少ないからだめなんですぅ、とおっしゃる方がいますが関係ないです。そもそも肺の大きさにそんなに差があるわけじゃないですから。肺活量が少ないということは、呼吸が下手ということなんですね(^_^;)。だから大丈夫、肺活量は多くすることが出来ます(^^)。
確かに言われてみれば、肺の大きさに個人差がメチャクチャあるわけがない。問題なのは姿勢と筋肉の使い方なんですよね。
■ 姿勢を良くする
良い声を出すためには絶対に必要です。練習の最初に当たり前のようにやっていますが、歌う際に、本当に正しい姿勢になっているかチェックする習慣はつけておきたいところです。
姿勢を良くする簡単エクササイズ2つ | 烏は歌う
後ろ姿に自信を!正しい姿勢とは #02 | 東京ナイロンガールズ
チェック法は背中を壁にできるだけぴったり付けること。胸が前に出ていると胸郭に十分な呼吸が入っていきませんし、腰が前に出ているようだと特に背中が膨らんでいきません。
■ 筋肉を使う
個人的に最大の収穫でした。腹直筋しか使っていなく、腹斜筋を使ってなかったんですね。腹斜筋ってなに?って人は同じサイトの以下のエントリーを参照。
腹から声を出す!
腹から声を出す!その2
いや本当にブレスが伸びてビックリしました。その2で紹介されているボイトレ的腹筋トレーニングは毎日、通勤中の車の中でやっています(笑)。ブレスが伸びるから何?っていう話もありますが、息に余裕ができることで曲の一つ一つのフレーズを楽に歌うことができますし、ロングトーンでの支えもしっかりしたと感じています。自分にこんな基本的なところで伸び代があるんだと実感できました。
合唱って、初めてやるときは歌い方をイメージで伝えられることが多いので、こういった勘違いとか見落としをこれからもできるだけ見つけていきます。
■ 声を出す仕組み
基本的な事として、声を出す仕組みについて確認します。声は呼気が声帯を通過することで生じます。声帯は伸縮させることによって音程の高低を制御することができます。この内容の詳細については以下のサイトが詳しいです。
声帯と声の関係 | 吟詠の為のボイストレーニング
なので、ブレスの勢いが足りていないと、そもそも十分な声量を出せません。声量が足りていないと、正しい音程でも個人アンサンブルではハモったように聞こえません。また、パート同士の音が聞こえないとピッチが狂っていくことが多いと思います。
でも肺活量の低い人って、声量を出そうとするとすぐに息が持たなくなりますよね。
■ ブレスを増やす
調べるまで、この辺りを勘違いしていました。「肺活量って個人差があるからな~」と思っていました。
9なぜ腹式呼吸が必要? | 声の豆講座
よく私は肺活量が少ないからだめなんですぅ、とおっしゃる方がいますが関係ないです。そもそも肺の大きさにそんなに差があるわけじゃないですから。肺活量が少ないということは、呼吸が下手ということなんですね(^_^;)。だから大丈夫、肺活量は多くすることが出来ます(^^)。
確かに言われてみれば、肺の大きさに個人差がメチャクチャあるわけがない。問題なのは姿勢と筋肉の使い方なんですよね。
■ 姿勢を良くする
良い声を出すためには絶対に必要です。練習の最初に当たり前のようにやっていますが、歌う際に、本当に正しい姿勢になっているかチェックする習慣はつけておきたいところです。
姿勢を良くする簡単エクササイズ2つ | 烏は歌う
後ろ姿に自信を!正しい姿勢とは #02 | 東京ナイロンガールズ
チェック法は背中を壁にできるだけぴったり付けること。胸が前に出ていると胸郭に十分な呼吸が入っていきませんし、腰が前に出ているようだと特に背中が膨らんでいきません。
■ 筋肉を使う
個人的に最大の収穫でした。腹直筋しか使っていなく、腹斜筋を使ってなかったんですね。腹斜筋ってなに?って人は同じサイトの以下のエントリーを参照。
腹から声を出す!
腹から声を出す!その2
いや本当にブレスが伸びてビックリしました。その2で紹介されているボイトレ的腹筋トレーニングは毎日、通勤中の車の中でやっています(笑)。ブレスが伸びるから何?っていう話もありますが、息に余裕ができることで曲の一つ一つのフレーズを楽に歌うことができますし、ロングトーンでの支えもしっかりしたと感じています。自分にこんな基本的なところで伸び代があるんだと実感できました。
合唱って、初めてやるときは歌い方をイメージで伝えられることが多いので、こういった勘違いとか見落としをこれからもできるだけ見つけていきます。